【シリーズ「葬儀の準備と費用対策」第3回】葬儀の種類と選び方|仏式、神式、無宗教葬など
こんにちは。終活アドバイザーのマコトです。私は葬儀社で10年間勤務し、数百件以上の葬儀に立ち会ってきました。
このシリーズ「葬儀の準備と費用対策」では、終活を始めたばかりの方に向けて、葬儀に関する情報をわかりやすくお届けしています。第3回となる今回は、「葬儀の種類と選び方」について詳しくお話しします。
「仏式」「神式」「無宗教葬」……聞いたことはあるけれど、実際にどう違うのかよくわからないという方も多いと思います。大切なご家族の最期をどう送りたいか、あるいはご自身がどのような形で見送られたいかを考える上で、知っておきたい内容です。

1. そもそも、葬儀の種類っていくつあるの?
日本で主に行われている葬儀には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 仏式葬儀(ぶっしき)
- 神式葬儀(しんしき)
- 無宗教葬
このほかにもキリスト教式や創価学会式などもありますが、今回は多くの方に共通する3つを中心に解説します。
2. 仏式葬儀とは? 日本で最も多い形式
日本の葬儀の約90%以上が仏式で行われていると言われています。お坊さんを招き、お経をあげてもらう形式で、故人の冥福を祈るスタイルです。

仏式の特徴
- 読経や焼香などが行われる
- 宗派によって作法や戒名が異なる
- お布施が必要(3万〜20万円程度が相場)
親族に仏教徒が多い場合や、「昔からの習わしを大切にしたい」という方には仏式が選ばれやすいです。
ただし、お布施の相場が不明確で不安という方は、定額でお坊さんを呼べる葬儀サービス![]() に相談しておくことで、安心して準備することができます。
に相談しておくことで、安心して準備することができます。
3. 神式葬儀とは? 日本の伝統を重んじる方に
神式は神道(しんとう)の形式で行われる葬儀です。仏教のような読経はなく、「祭詞(さいし)」という言葉で故人の魂を慰める儀式が行われます。
神式の特徴
- 神職(しんしょく)が進行する
- 焼香の代わりに「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」を行う
- 戒名ではなく「諡(おくりな)」が授けられる
「先祖代々が神道」「神社にゆかりがある」という家庭では、神式が選ばれることもあります。仏式とは違う作法があるため、式の進行をサポートしてくれる葬儀社選びが大切です。
全国の葬儀社を案内できるサイト![]() で、神式の経験が豊富な葬儀社を探すのがおすすめです。
で、神式の経験が豊富な葬儀社を探すのがおすすめです。

4. 無宗教葬とは? 自分らしく送りたい方に人気
最近増えているのが「無宗教葬」。読経や宗教者を呼ばず、自由なスタイルで故人を見送る葬儀です。
無宗教葬の特徴
- 進行は司会者または家族が行う
- 音楽を流したり、手紙を読んだりできる
- 宗教的な儀式がない分、費用が抑えられる
「家族だけで静かに見送りたい」「宗教にこだわりたくない」という方に選ばれています。式の内容に決まりがない分、事前にしっかりプランを考えることが大切です。
最近では、エンディングノートに希望の葬儀内容を書いておく方も増えています。
|
|
5. 自分に合った葬儀の選び方
「どの形式が正解か」という決まりはありません。大切なのは、ご本人やご家族が納得できる形を選ぶことです。
以下のようなポイントを参考にすると、選びやすくなります。
- 家族や親族の意向:親戚に強いこだわりがある場合は話し合っておく
- 費用面:宗教者を呼ばない無宗教葬は比較的安く済む
- 地域の風習:地域によって「この形式が一般的」ということもある
最終的には「こんな風に送りたい」「こんな風に送ってほしい」という気持ちを整理することが、後悔しない葬儀選びにつながります。
そのためにも無料の資料請求![]() や葬儀の相談サービスを活用して、自分に合う葬儀社を探してみましょう。
や葬儀の相談サービスを活用して、自分に合う葬儀社を探してみましょう。

6. まとめ:自分や家族に合った葬儀を選ぶために
今回は「仏式」「神式」「無宗教葬」という3つの主な葬儀スタイルと、その選び方についてお話ししました。
一人ひとりに合ったお見送りの形があります。だからこそ、「どの形式が合うのか」を知ることが、終活の大切な一歩になります。
次回の第4回では、「葬儀を事前に契約するメリットとデメリット」について詳しくお話ししていきます。
「終活の中で、契約はどこまでしておくべきか?」という不安をお持ちの方に向けて、具体的な判断ポイントをお伝えします。ぜひお読みください。


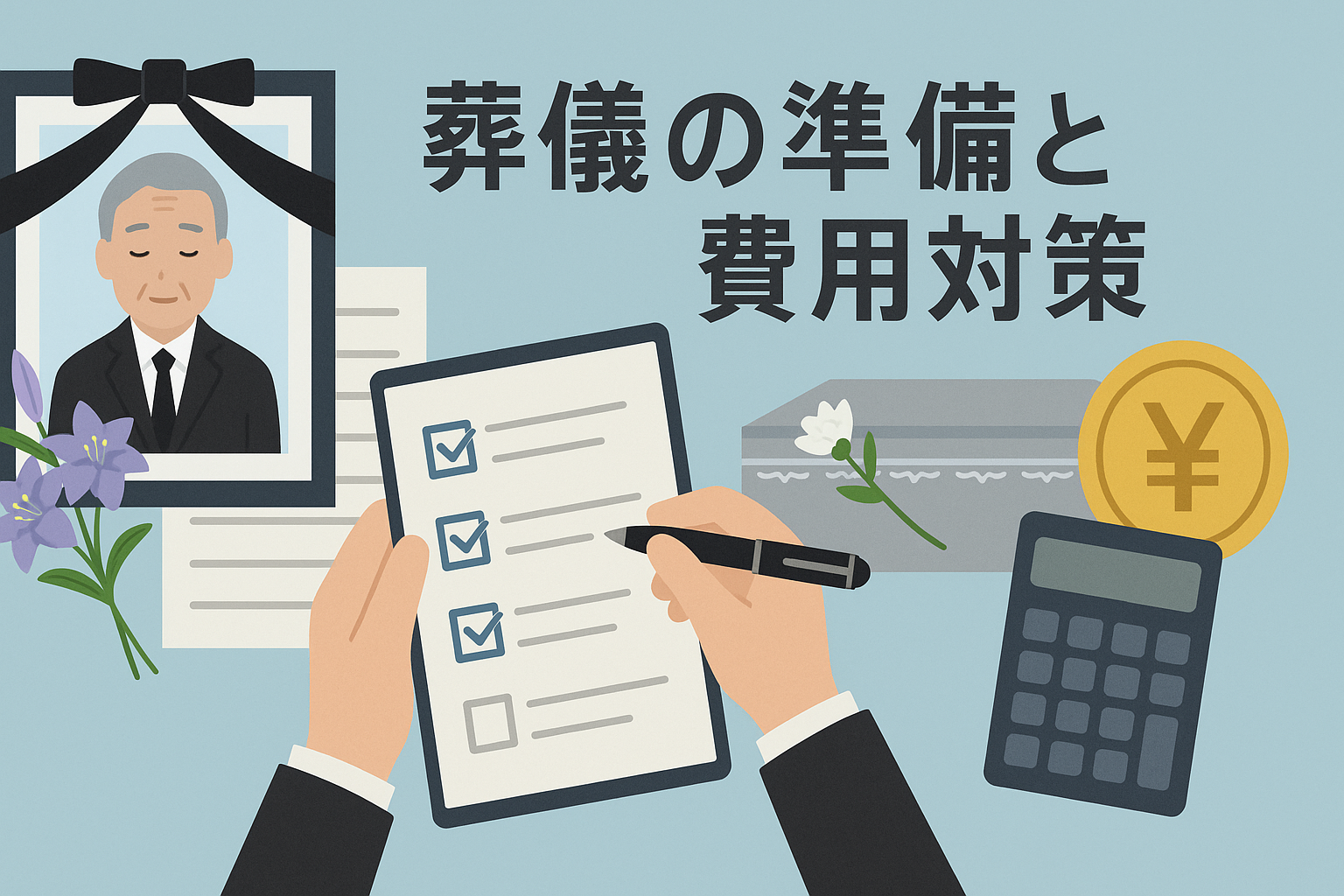


コメント